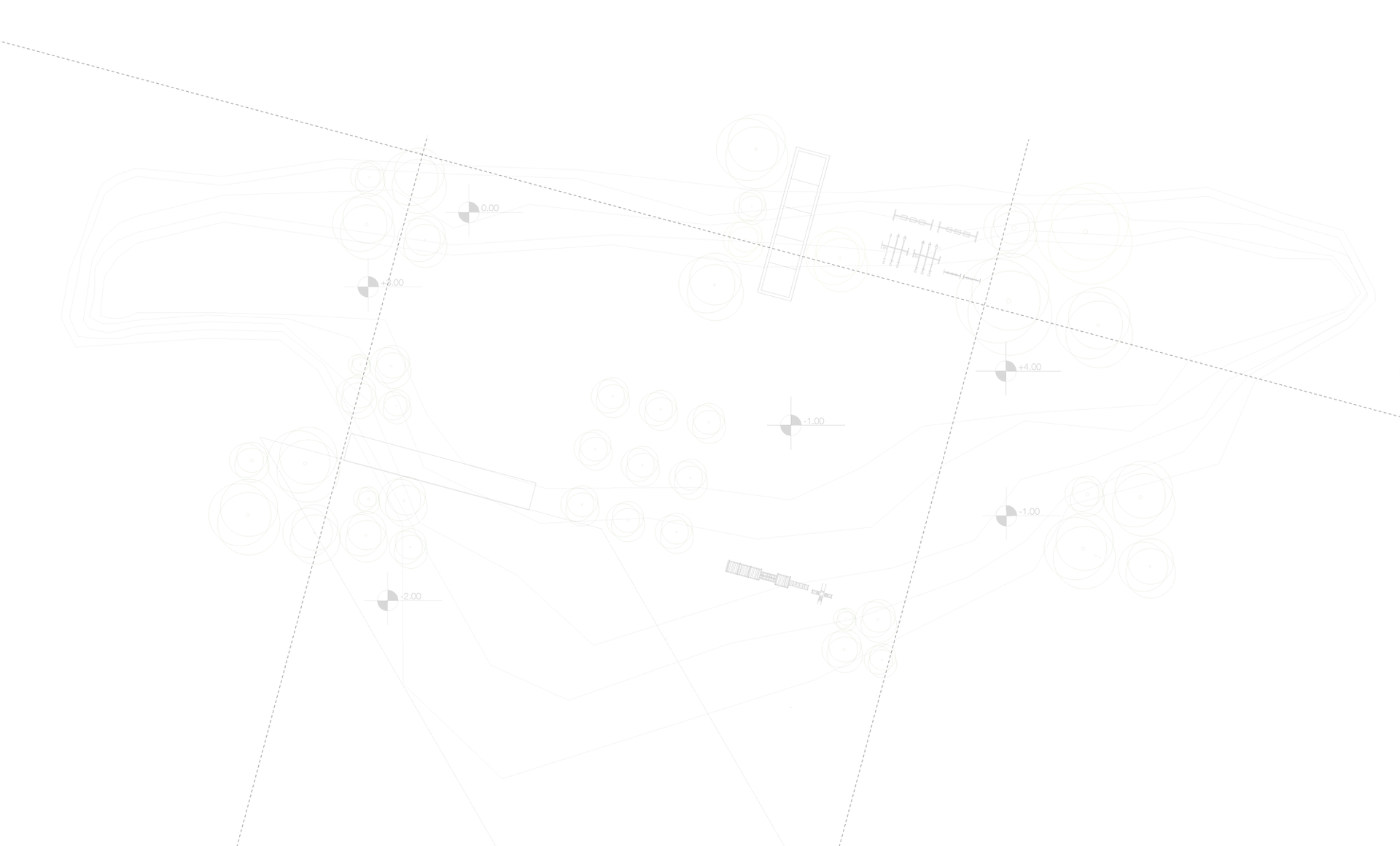
主な研究テーマ
1.積雪寒冷地におけるリンゴ園の土壌
管理について(秋肥の必要性の検討)
日本全国のリンゴ生産量の約57%に相当する約47万tは青森県産であり、その生産量は毎年第1位を維持しています。本県は冬期間の降雪量が多いので、融雪後に施肥を行う「春肥」が施肥基準として推奨されています。その理由は、他県で実施されている秋肥を本県において実施すると、春先の融雪水により施肥窒素が土壌深部へと溶脱するためです。秋肥は、翌春の花芽および新梢の初期生育を促進させる重要な役割を担っています。このため、融雪季初期においてもリンゴ樹の根が肥料成分を欲していることから、青森県以外では生産者に対して秋施肥の実施を指導している状況にあります。しかし、その一方で、青森県内のリンゴ生産者からは、秋施肥を実施しないで春施肥のみ実施することに対する疑問が呈されているのが現状です。積雪地域の果樹生産においては、秋肥および春肥の施用による無機態窒素の浸透流出挙動の詳細は明らかにされていないため、樹園地における窒素循環機構が解明されていません。したがって、この研究を行うことによって、果樹の生育面と土壌の環境面の双方から推奨できる、施肥体系や土壌管理技術を確立することが将来的に可能になると考えています。
※ 2011年4月~研究
2.大規模整備型畑地におけるナガイモ
の塊茎障害の発生抑制について
青森県上北地域(特に、十和田市と東北町)および西北地域(特に、旧車力村と旧豊富村のつがる市)の根菜類(ナガイモ・ゴボウ・ニンニク等)の品質向上を目的とした、畑地基盤整備の在り方を検討しています。具体的には圃場の効果的な排水技術の導入を目指しています。
※ 2012年4月~研究
3.津波被災地域における塩害農地の
修復と地下水水質改善について
青森県三八地域の塩害農地土壌と高EC地下水水質の改善を目的に、低コストで効率的な農地の除塩方法を開発しています。
このグラフは、青森県三八地域の塩害農地土壌における土壌間隙水のCl濃度の位置的・時間的変化を表しています。最上のグラフは日蒸発散量と日降水量(mm/day)、イソプレットの縦軸は土壌深度(cm)、横軸は月、▼印は東日本大震災で発生した津波、▲印は豪雨による高潮、カラースケールはCl濃度(mg/L)を表し、白色が10000 (mg/L)以上、黒色が0 (mg/L)です。当該地区の農地は地下水位が高く、また、海岸から400m程度しか離れていないため、海水を含んだ地下水の影響を強く受けることから、地下水位低下・土壌水の排水を促進させるため、明渠や暗渠を敷設することが必要であることがわかります。
※ 2011年4月~研究
4.農地土壌の環境観測ツールの開発
上記1~3の研究を実施する際に、現場や実験室内で行う実験で有用となる計測器や計測方法を開発しています。このセンサを使うことで、土壌中の流体輸送ベクトル・熱物性・体積含水率および電気伝導率を同時に計測することができます。現在、実用化に向けて計測方法を改良しています。
※ 2003年4月~研究

このグラフは、黒ボク土農耕地における土壌間隙水のNO3-N濃度の位置的・時間的変化を表しています。最上のグラフは日降水量(mm/day)、イソプレットの縦軸は土壌深度(cm)、横軸は月、▼印は施肥のタイミング、カラースケールはNO3-N濃度(mg/L)を表し、白色が50 (mg/L)以上、黒色が0 (mg/L)です。樹園地(Type G)や野菜作の農耕地(Type C, D)では追肥回数や施肥量が多いです。これらの農耕地では、春先~梅雨時季の降水によって、土壌中に残存しているNO3-Nが土壌深部へと一挙に浸透流出していくことがわかります。

生物共生教育研究センター藤崎農場リンゴ園での土壌サンプリングの様子

十和田市内のナガイモ畑の様子
2012年9月撮影

つがる市内のナガイモ畑で間隙水を採水中
2016年10月撮影



高EC地下水の現場水質測定
塩害農地土壌の降水による現場除塩実験

QPHPセンサを用いた塩害農地現場での体積含水率・電気伝導率・熱物性の同時計測の様子

